【PR】本記事にはプロモーションが含まれていません。
離婚後の親子関係や子育てで「共同親権の法改正」がどう影響するのか、養育費・面会交流などの制度運用がどう変わるのか、不安に思っているひとり親の方も多いと思うので、2026年(令和8年)施行予定の改正内容を、一次情報をもとに、できるだけわかりやすく整理しました。
 ゆいなん
ゆいなん私自身も「子どもの将来」「生活の安定」を考える中で、この法改正を知っておきたかった内容だったので、同じように悩んでいる方の助けになればと思っています。
- 共同親権とは何か、今回の法改正で具体的に何が変わるのか
- 養育費・面会交流に関する新しいルールや押さえておきたいポイント
- 法改正への準備で、今からできること
共同親権の法改正とは?2026年から始まる新ルール
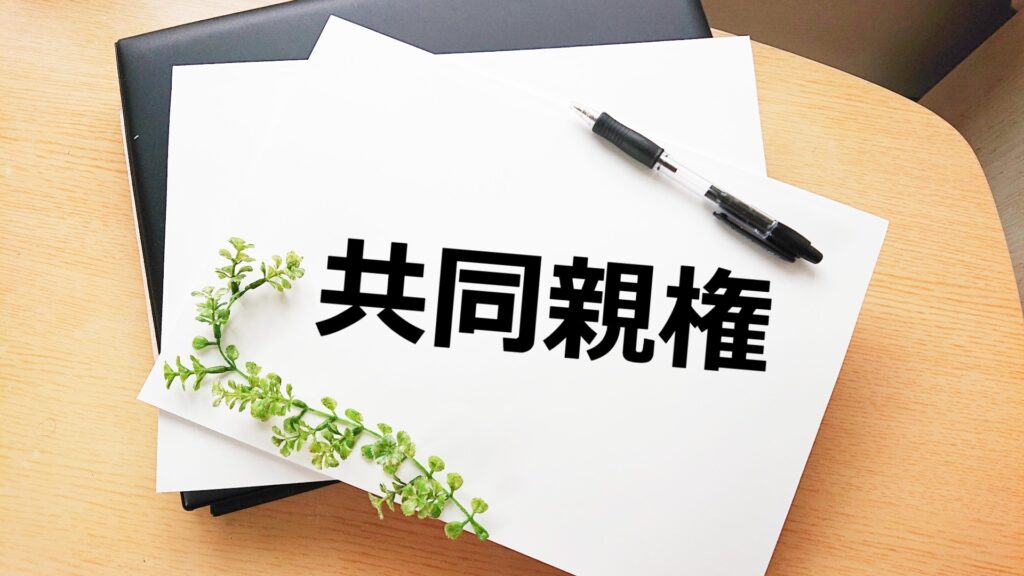
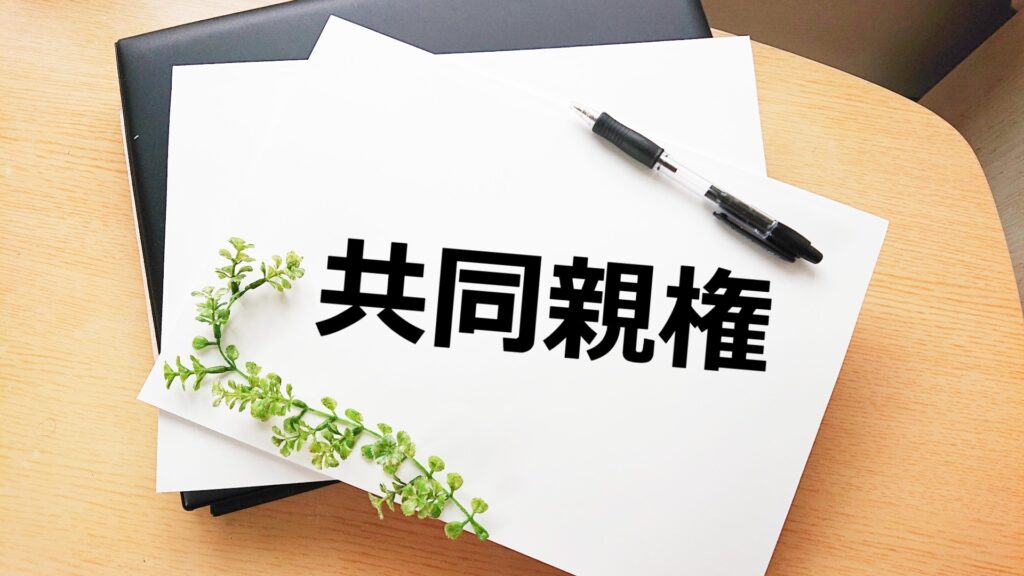
親権制度・法改正の背景
- 2024年(令和6年)5月17日、「父母の離婚後の子の養育に関するルール」を見直す民法等の一部改正法が成立。(法務省)
- この改正の目的は、「離婚後も子どもの利益を確保すること」。父母の責務を法律で明らかにし、養育費・親権・面会交流などでこれまであいまいだった部分を整理すること。
- 法改正は 親権(単独親権・共同親権)、監護、養育費、親子交流(面会交流)、養子縁組、財産分与など多くの項目に関わる。
- 施行時期は 令和8年(2026年)5月までに行われる予定。
共同親権とは何か
- 離婚後はどちらか一方が親権者になる「単独親権」が前提でした。
つまり、法律上、子どもの重要な決定(学校、住居、医療など)は親権者が一人で行う形。
- 両親が話し合いで合意すれば、離婚後も「共同親権」を選択できるようになります。
子どもの利益に配慮した運用が前提(法務省)



親権って子どもを守る大切なルール。だからこそ“自分の家庭にはどう影響するのか”を知っておくことが大事です。
共同親権法改正で養育費はどう変わる?【2026年の変更点】


親の責務の明文化
親が子どもを養育する責任(養育義務・生活保持義務など)が、法律でより明確に規定されます。これにより、「親だから、何となく義務がある」ではなく、法律上の責任として認められる形に。
法定養育費(仮称)の創設(見込み)
養育費の取り決めがされていない、あるいは話し合いが難しいケースでも、「省令で定める基準」に基づく法定養育費が導入される方向。最低限の目安が示される見込みです。
この法定養育費には先取特権が付与され、未払い時の回収で優先的に権利を行使できる仕組みが想定されています。(制度設計の詳細は今後公表予定)
強制執行・回収ルートの改善
現行は、養育費を確実に回収するには「債務名義」(執行認諾付き公正証書、調停調書、審判書、判決書など)が必要。
改正後は、上記の先取特権や財産開示制度の強化により、回収手続きのハードルが一部下がる見込み。収入や財産の開示に応じない場合の過料など、実効性確保の仕組みが強化されます。(法務省)



養育費は子どもの生活そのもの。少しでも“受け取りやすい仕組み”になるのは心強いですよね。
すんなり養育費のことが決まっても口約束のみの取り決めはやめましょう。残念ながら、途中から支払われないケースもよく聞かれます。
私は公正証書に残す前に相手と連絡が取れなくなり、養育費は支払われず、給与の差し押さえもできませんでした。
公正証書など、きちんと書面に残すことをおすすめします。
- 法務省:公証制度(公正証書の基礎)
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji30.html - 法務省:公正証書を作成するには?
https://www.moj.go.jp/MINJI/1-1-1-2-2-1.html - 日本公証人連合会:公正証書とは/準備書類Q&A
https://www.koshonin.gr.jp/notary/ow01
https://www.koshonin.gr.jp/notary/ow11/11-q01
共同親権法改正で面会交流はどう変わる?安全配慮のルールも解説


親子交流(面会交流)の考え方が明確化。話し合いで決められない場合は、家庭裁判所が「子の利益」を最優先に調整。
DV・虐待等の安全配慮が必要な場合には、面会交流・親権運用に例外・制限が設けられる仕組みを維持(強化)。



面会交流は“子どもの心の安定”につながる一方で、無理のない形を選ぶことが大切です。
私は面会交流や養育費の取り決めをしている最中に、元パートナーが連絡を断って逃げてしまいました。
離婚後一度も養育費は支払われず、面会交流もしていませんが、現在のところ子どもの精神面は安定しています。
共同親権法改正のメリット・注意点は?ひとり親が知っておきたいこと
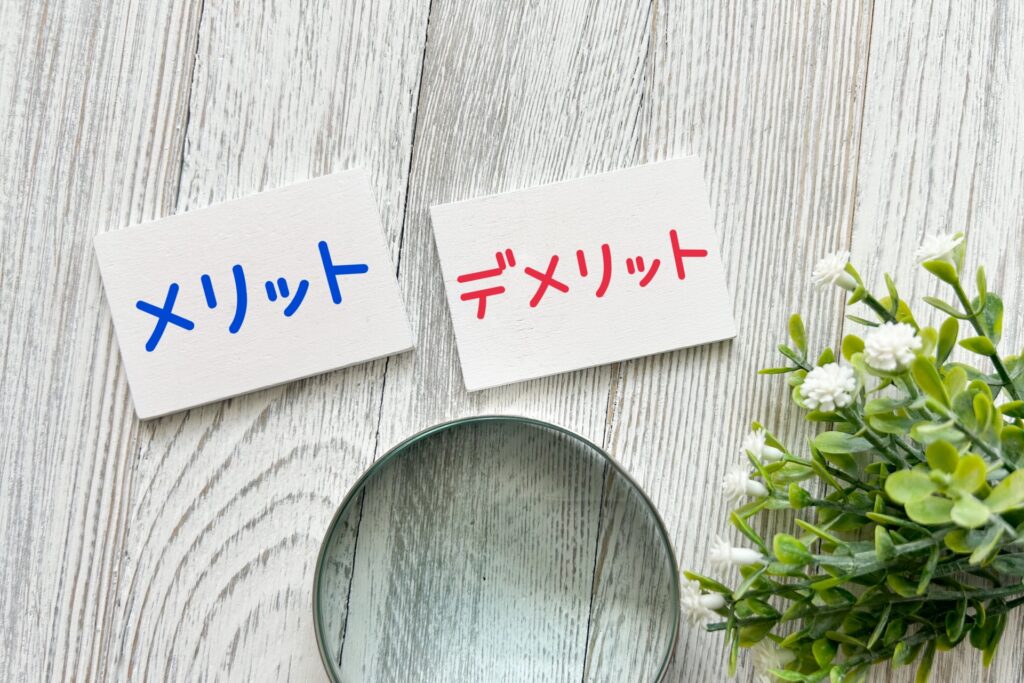
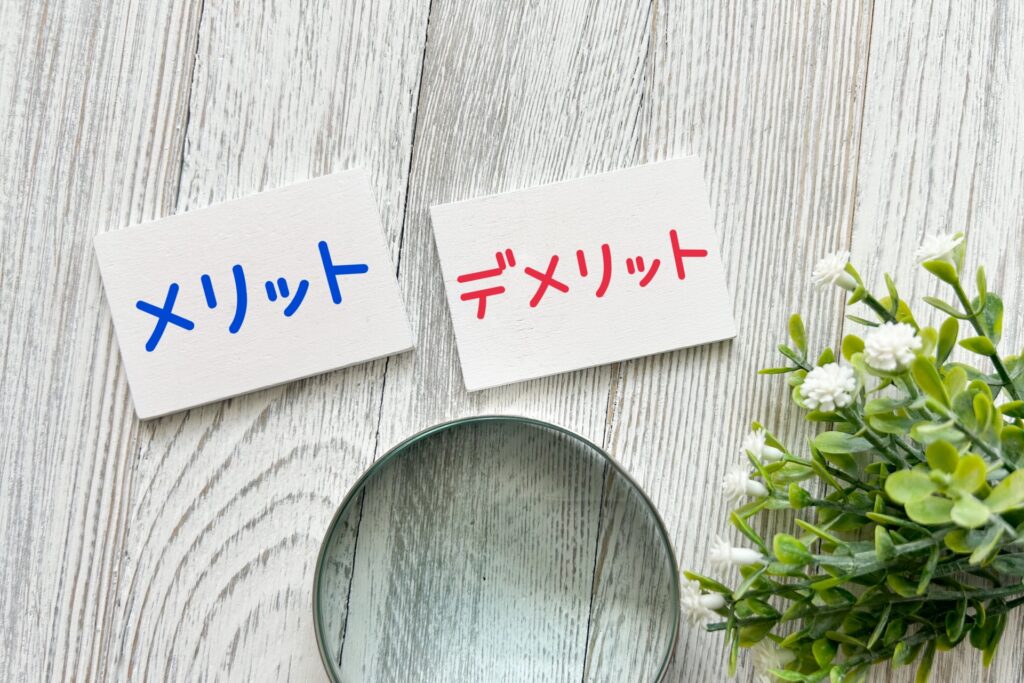
| メリット | 注意点 |
|---|---|
| 養育費の回収可能性が上がる(先取特権、実効性確保策) | 制度を使うには「取り決めを文書化」しておくことが前提になりやすい |
| 最低基準が示され、養育費額交渉の出発点が明確に | 法定養育費の額や細目は今後の公表待ち。個別事情で増減あり |
| 面会交流のルールが整理され、子の安定に資する可能性 | 協議が難航すると、裁判所関与→時間・コスト・心理的負担が増える |
| DV・虐待等には例外規定が機能する想定 | 実務(家庭裁判所・公証・弁護士等)の知識・手間は依然必要 |



メリットばかりに見えても、実際は家庭ごとに事情が違います。“うちの場合はどうか”を考える目線を忘れないでくださいね。
共同親権法改正に向けて今からできる準備5ステップ


- 取り決めは文書で残す
可能なら「執行認諾文言付き公正証書」や「調停調書」等を用意。口約束だけは避ける。 - 収支の資料を整える
自分の家計はもちろん、相手の収入が推測できる資料(源泉徴収票・給与明細等)があると交渉・審理で有利。 - 法律相談・自治体相談を活用
ひとり親支援窓口、法テラス、自治体の無料法律相談などへ。
・法テラス:離婚を考えたときに知っておきたいこと(親権・養育費など)
https://www.houterasu.or.jp/ - 協議の履歴を残す
面会交流・費用分担の意向ややり取りをメモ・メールで記録。 - 一次情報の更新を定期チェック
省令・運用基準・裁判所実務はこれから詳細が出るため、法務省ページをブックマーク:
・法務省 民事局「共同親権等に関する改正」総合案内
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00357.html



準備は大きなことじゃなくても大丈夫。“記録を残す”だけでも、後の安心にきっとつながります。
まとめ|共同親権法改正で変わる養育費・面会交流と準備の大切さ
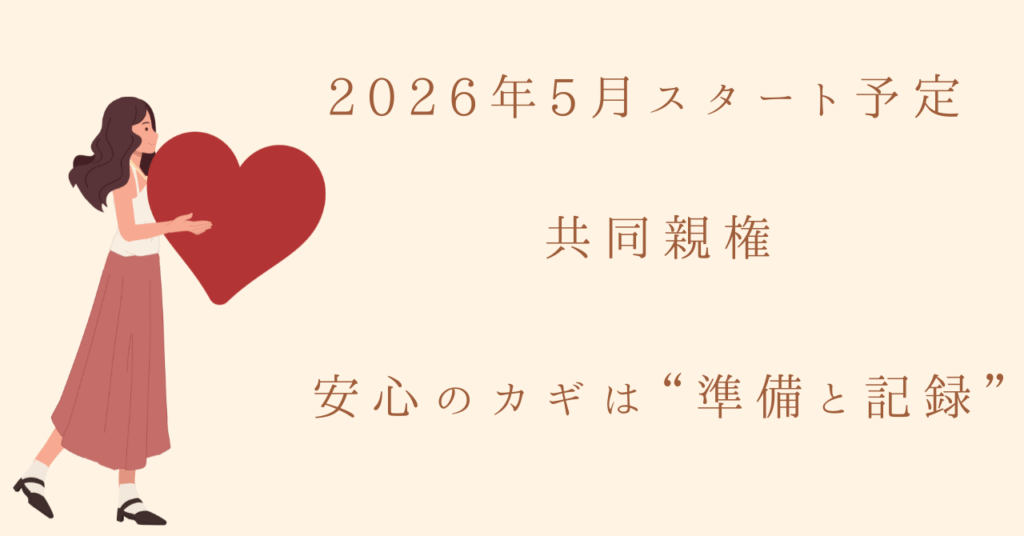
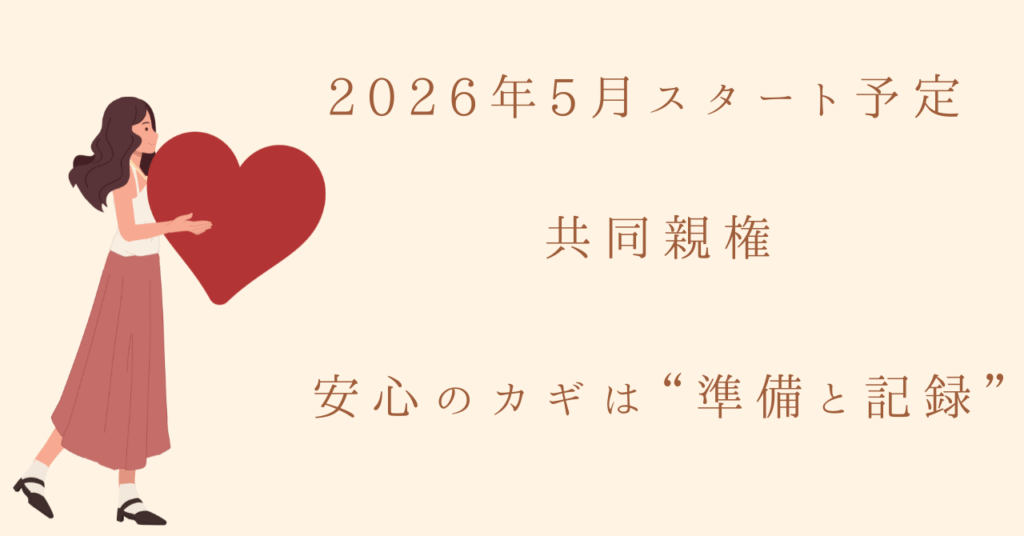
共同親権の法改正は、2026年5月までに施行される予定で、親権の選択肢が増えるだけでなく、養育費の実効性や面会交流のルール明確化など、子どもの利益を守るための実務が強化されます。
一方で、最終的に暮らしを守るのは「準備」と「記録」。
取り決めの文書化・証拠の整理・相談窓口の活用で、制度を“使える形”にしておくことが、ひとり親家庭の安心につながります。
制度が変わっても、子どもを守れるのは“あなたの一歩”から。私も一緒に準備していきますね。
参考リンク
- 法務省:民法等の一部を改正する法律(共同親権ほか)総合
- https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00357.html 法務省
- 法務省パンフ:父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました(PDF)
- https://www.moj.go.jp/content/001428136.pdf 法務省
- 法テラス:養育費・婚姻費用(よくある相談)
- https://www.houterasu.or.jp/site/faq/youikuhi-konpi.html 法テラス
- 法テラス:ひとり親向け 養育費の相談案内
- https://www.houterasu.or.jp/lp/2024hitorioyashien/ 法テラス
- 内閣府(政府広報):養育費と親子交流の基礎解説(合意書の作り方等)
- https://www.gov-online.go.jp/article/201611/entry-9004.html 政府広報オンライン
- 内閣府(規制改革会議 資料/養育費履行確保の取組・実態調査:PDF)
- https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2201_02human/220328/human05_0105.pdf
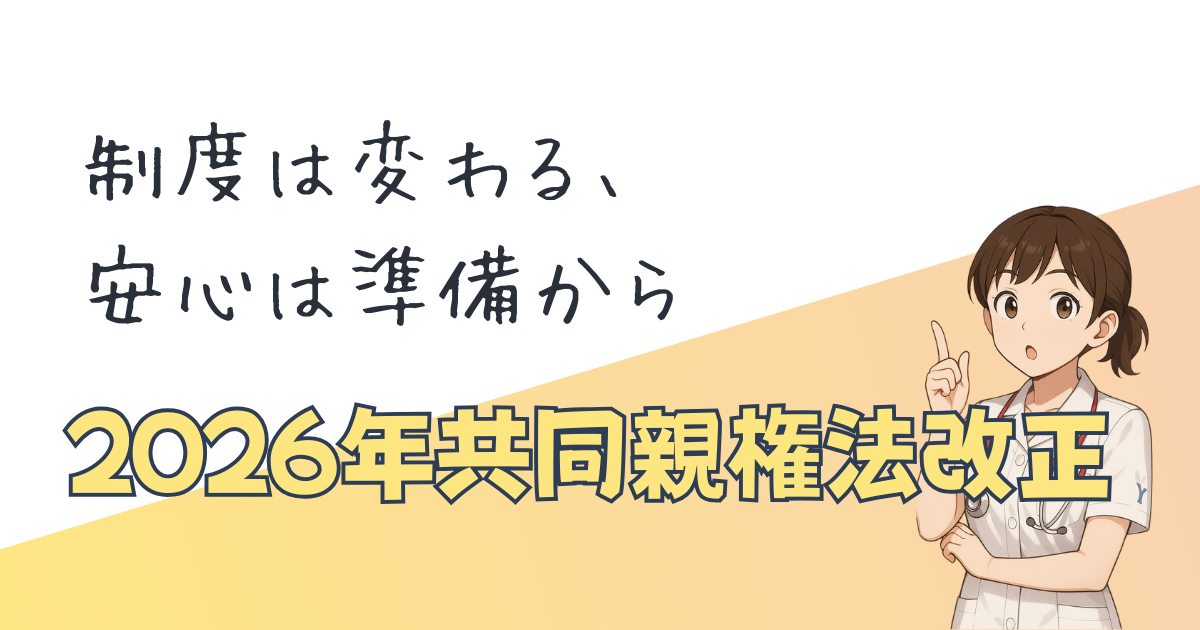
コメント