【PR】本記事にはプロモーションが含まれています。
夜勤や交替制勤務をこなしながら、出産・育児を迎える看護師ママ。

共働きじゃないと支給されないの?



シフト勤務でも対象になるの?
そんな声が増えています。
2025年4月から始まった出生後休業支援給付金は、育休中の収入を少しでも補うための新制度です。
ただ、条件や例外が複雑で「私も対象になるの?」と迷う方も多いのが実情。
本記事では共働きでなくても支給されるケースやシフト勤務でも対象になる条件を、看護師ママの視点でやさしく整理します。
- 出生後休業支援給付の基本と支給条件
- 共働きでなくても対象になる例外ケース
- シフト勤務・単独取得での注意点
- 申請のタイミングとQ&A
出生後休業支援給付とは?|2025年スタートの新しい育休支援


「出生後休業支援給付金」は、育児休業給付(67%)に13%を上乗せし、実質的に手取り10割に近づけることを目的とした新制度です。
最大28日間
上乗せ額は賃金日額 × 日数 × 13%
対象は、育児休業給付または出生時育児休業給付の支給対象である雇用保険被保険者です。制度の狙いは「産後早期の共同育児の後押し」で、父母それぞれ14日以上の育休が原則となります。



新制度は“育休67%+上乗せ13%”で最大28日分を補う仕組みです。
産後の生活を支える意図があり、基本は父母それぞれ14日ずつの取得が前提です。
ただし後述のとおり、状況次第で“単独でも対象”になり得ますので安心してください。
共働きが条件?|原則は「父母で14日ずつ」取得


原則条件は次の2点です。
- 同一の子について、出産日(または予定日)から一定期間内に父母それぞれ14日以上の育休を取得すること。
- 本人の休業は、育児休業給付または出生時育児休業給付の対象となる休業であること(単なる休暇・欠勤は不可)。
つまり「片方が14日未満」では原則対象外ですが、制度には配偶者要件を外せる例外が設けられています。



“共働きが必須”というより、まずは原則の考え方を押さえておきましょう。
本人側の休業が『給付対象の育休』であることが大前提になります。
このあと紹介する例外に当てはまれば、単独での受給ルートも検討できます。
共働きじゃなくても対象になる?|配偶者要件を外せるケース
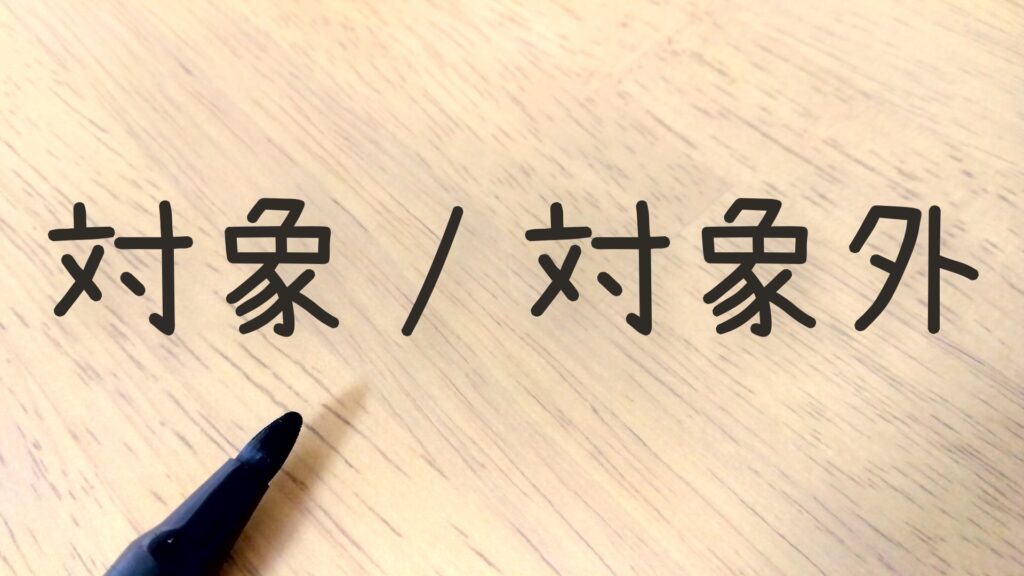
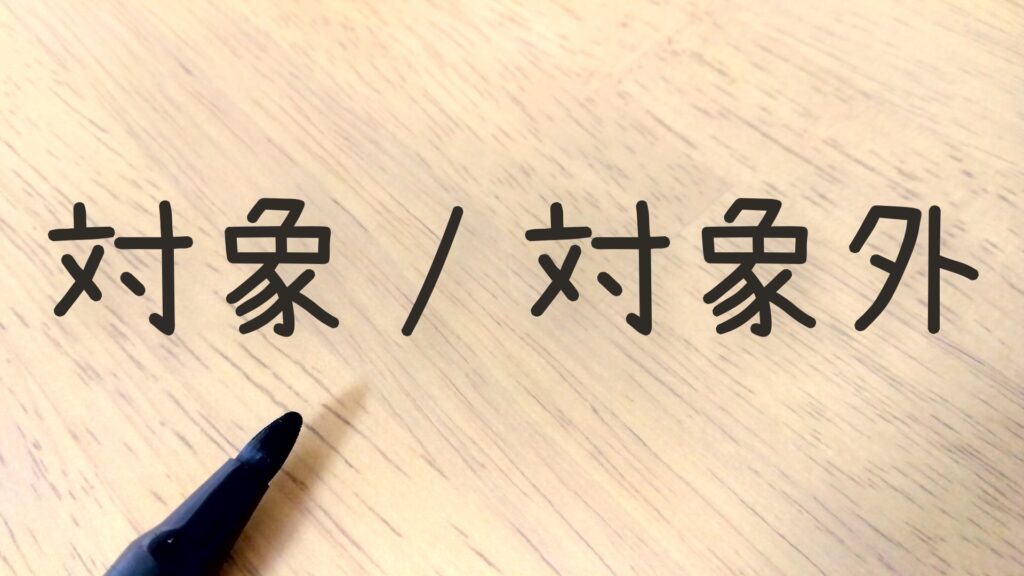
厚労省資料には**「配偶者の育児休業を要件としない場合」**が明記されています。これは、例外的に単独で申請できることを意味します。主なケースは次のとおりです。
| 状況 | 扱いの目安 |
|---|---|
| 配偶者が雇用保険の被保険者でない(専業・無職・フリー等) | 本人単独で申請可能 |
| ひとり親・別居・DVなどの事情 | 配偶者要件の適用除外 |
| 配偶者が産後休業中など育休取得が困難 | 要件を課さない扱いとなることあり |



ひとり親の方や、配偶者が被保険者でない場合は“配偶者要件なし”で進められます。
別居・DVなどのやむを得ない事情でも、例外が認められることがあります。
実際の適用は窓口判断になりますので、労務やハローワークで個別に確認しましょう。
シフト制・交替勤務でも受け取れる?|看護師ママの注意点


勤務形態(シフト制・夜勤あり)を理由に除外されることはありません。
重要なのは、休業の取り方と申請手続きが要件に合致しているかです。次のポイントを必ず確認しましょう。
- 正式な育休申請を行っているか(シフト調整や有給の組み合わせだけでは不可)
- 休業中の勤務日数が基準内か(一定日数を超えて働くと“休業”と認められない場合あり)
- 賃金日額の算定は妥当か(夜勤・深夜手当を含む直近6か月平均で確認)
- 産後休業→育休の切り替え時期が明確か(就労記録・シフト表の保存)



シフト制でも、育休としての“実体”が整っていれば問題ありません。
出勤簿や賃金台帳など、証拠書類をていねいに揃えておくと安心です。
夜勤手当の扱いなど計算根拠は、事前に労務担当とすり合わせておきましょう。
単独申請はできる?|後から配偶者が育休を取った場合
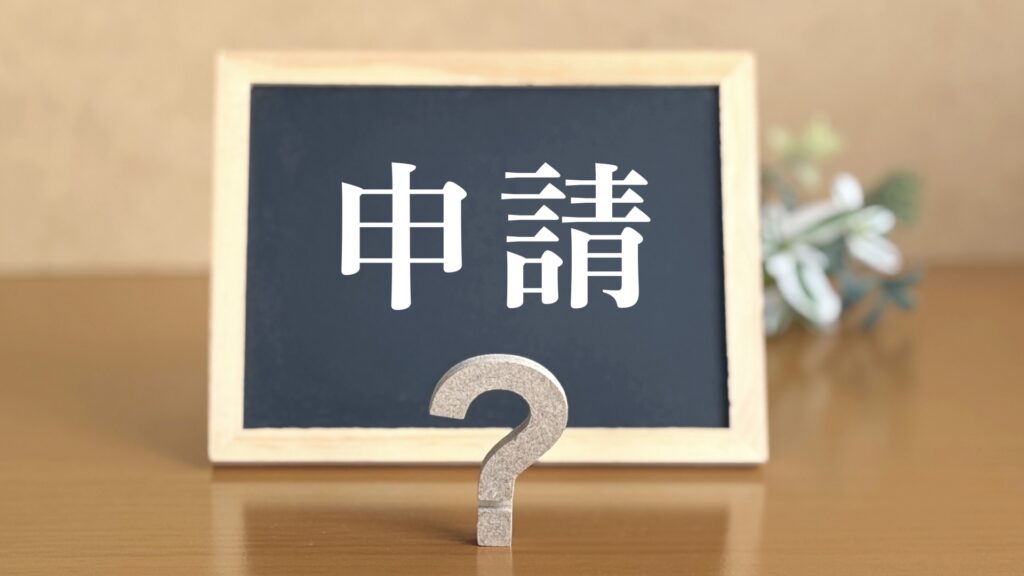
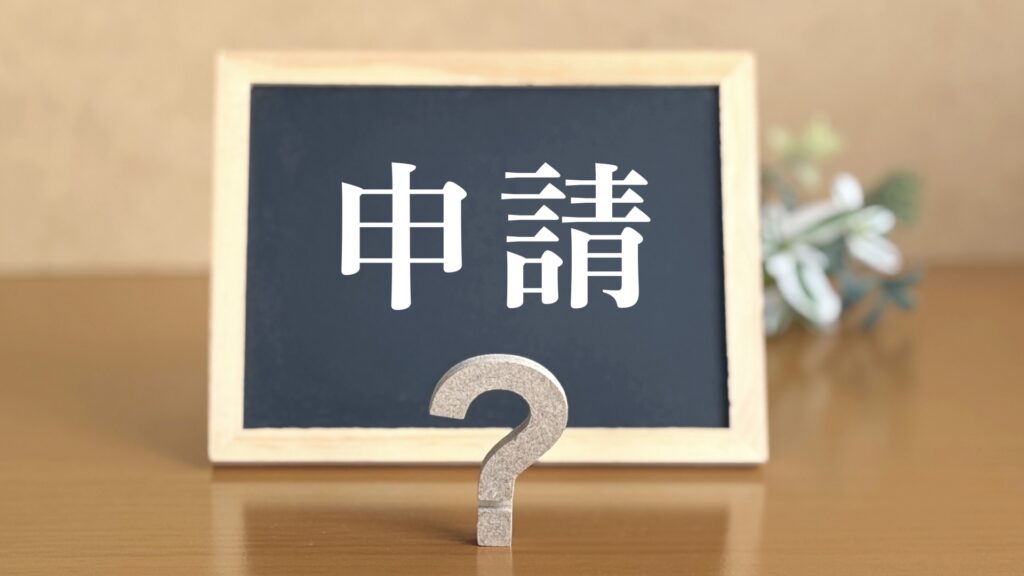
原則は、育児休業給付(または出生時育児休業給付)と同時申請です。
ただし、本人の育休給付が先に決定し、後から配偶者が14日以上取得して要件を満たした場合、出生後支援給付のみ追加申請できる運用が案内されることがあります。
新設制度ゆえにハローワークの運用差が生じやすいため、事前に窓口確認を行いましょう。



まずはご自身の育休給付を確実に進めるのが第一歩ですね。
配偶者の取得時期によっては、あとから“出生後給付だけ追加”の選択肢もあります。
期限や必要書類は窓口で最新情報を確認し、取りこぼしを防ぎましょう。
申請の流れとタイミング


| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 提出先 | 勤務先経由でハローワーク |
| 申請期限 | 育休開始から4か月以内(目安) |
| 必要書類 | 育児休業給付申請書、賃金台帳、出勤簿、母子手帳の写し等 |
| 相談先 | 会社の労務・社労士・最寄りのハローワーク |
| 注意点 | 新制度のため、地域・企業で運用が異なる可能性あり |



“育休開始から4か月以内”を目安に、余裕を持って準備しましょう。
会社経由の提出が基本ですので、早めに労務へ連絡して段取りを整えると安心です。
不明点はハローワークで最新運用を確認し、書類不備を避けていきましょう。
よくある質問(Q&A)


- 共働きじゃないと支給されませんか?
-
原則としては「父母それぞれ14日以上の育休を取ること」が条件ですが、ひとり親の方や、配偶者が雇用保険に入っていない場合(専業主婦・パート・フリーランスなど)は、配偶者の育休がなくても申請できるケースがあります。
また、別居・DVなどの事情がある場合も、配偶者要件が免除されることがあります。 - シフト勤務・夜勤ありでも大丈夫?
-
勤務形態は関係ありません。日勤・夜勤・交替制勤務などでも、「正式な育休申請」をしているかどうかがポイントになります。
シフト調整や有給休暇の組み合わせだけだと、休業として認められないことがあります。
また、育休中に働いた日数が多いと「休業ではない」と判断される場合もあるため、勤務日数の管理と出勤簿の保存が大切です。
看護師のように勤務形態が複雑な職種でも、きちんと書類を整えれば問題なく申請できます。 - 夫が後から育休を取った場合は?
-
本人の育児休業給付がすでに決定している場合でも、配偶者が後から14日以上の育休を取れば、出生後休業支援給付を“追加申請”できる場合があります。
ただし、地域のハローワークごとに運用が異なるため、後から追加が可能かどうかは必ず確認が必要です。
提出期限(育休開始からおおむね4か月以内)を過ぎると対象外になることもあるので、早めの相談が安心です。 - どこで申請するの?
-
申請先は勤務先経由でハローワークです。
基本的には、勤務先の労務担当者が「育児休業給付」の書類をまとめて提出します。
個人で直接行うことも可能ですが、会社を通す方がスムーズです。
必要書類(賃金台帳・出勤簿・母子手帳の写しなど)は、勤務先と連携して早めに準備しておくと安心です。



迷ったときは、労務とハローワークの“二方向相談”が近道です。
ご自身の状況が例外に当てはまるか、根拠と書類を揃えて確認していきましょう。
追加申請の可能性もありますので、時系列の整理も一緒に進めると安心です。
まとめ|共働きじゃなくても諦めないで
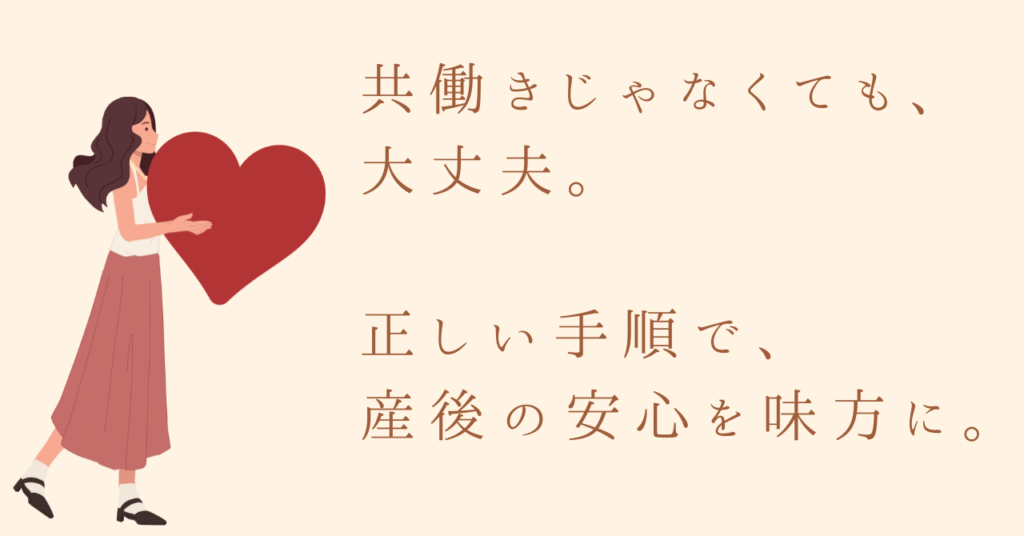
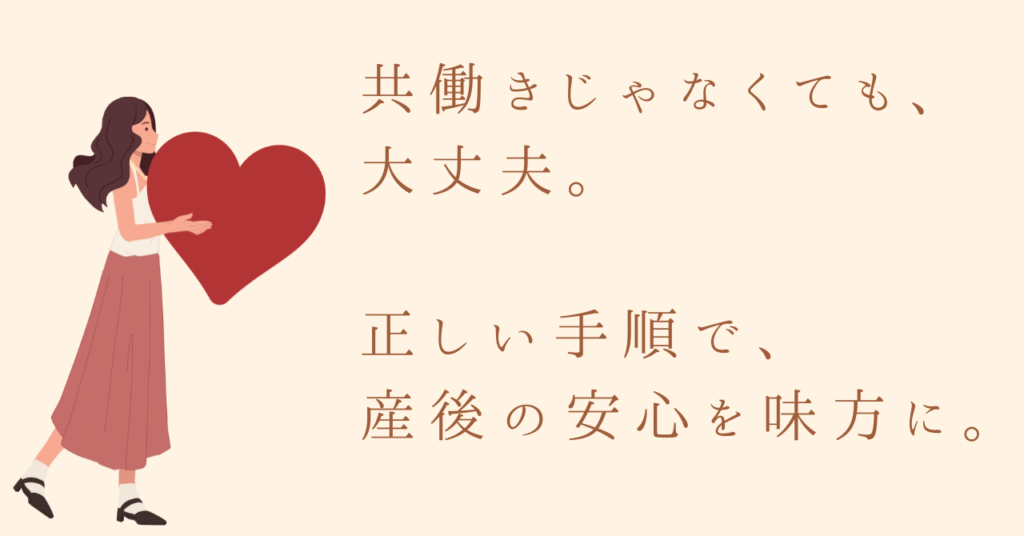
- 出生後休業支援給付は父母とも14日以上の育休が原則ですが、配偶者要件の例外により、ひとり親や配偶者が被保険者でない場合などは単独でも受給可能です。
- シフト制・夜勤ありの看護師でも、育休としての実体・手続きが整っていれば対象に乗ります。
- 新設制度で運用差が出やすい時期なので、ハローワークと労務に早めに相談し、余裕を持って準備を進めましょう。
“共働きじゃない=不可”ではありません。まずは条件を丁寧に確かめましょう。
シフト制でも、書類整備と勤務実態の管理でしっかり対応できます。
期限と運用差に気を配り、早めの一歩で安心につなげていきましょう。
参考リンク(一次情報)
- 厚生労働省|出生後休業支援給付の概要
- 厚生労働省|育児休業給付(制度全体の説明ページ)
- 政府広報オンライン|共働き家庭を支援する新しい給付制度
- ハローワークインターネットサービス|育児休業給付の詳細・相談窓口一覧
「共働きじゃないけど、制度を使って少しでも安心したい」
そんな方は、まずは情報収集から始めてみませんか。
育休や転職の相談もしやすい【ナースJJ】で、自分に合う働き方をチェックしましょう。
👉 ナースJJで求人を見る(公式サイト)
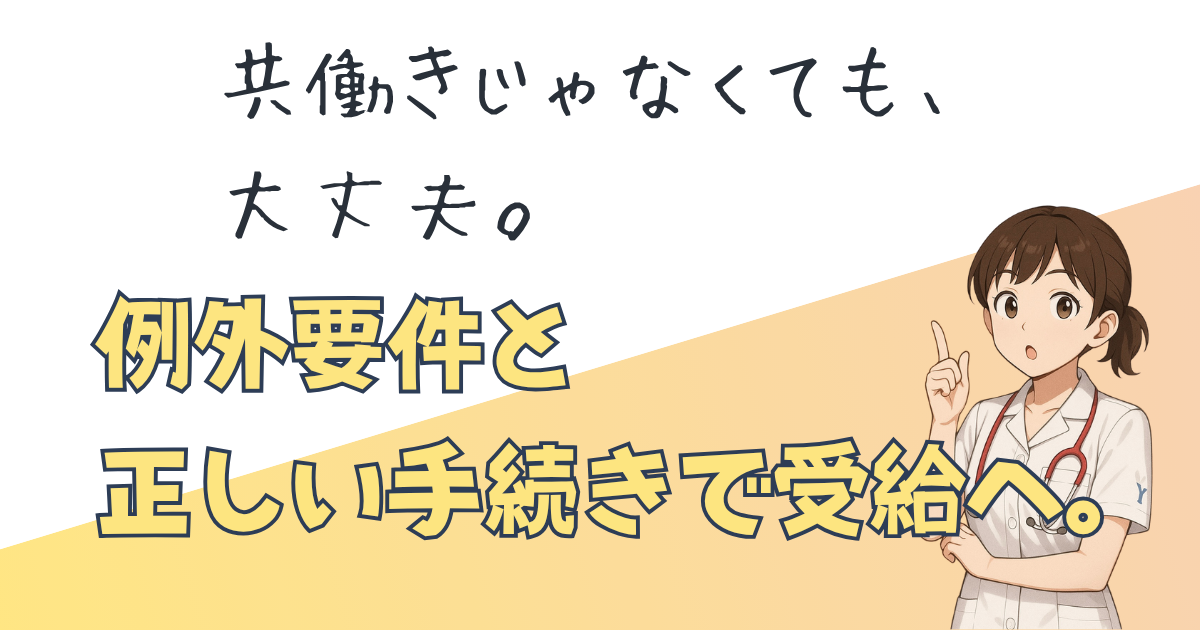
コメント