【PR】本記事にはプロモーションが含まれています。
夜勤、送り迎え、家事……。
毎日を一人でこなす中で、ふと

家賃がもう少し安ければ
と感じる瞬間、ありませんか?
看護師として働いていても、夜勤手当やシフトの変動で家計が安定しにくいのが現実。
とくに ひとり親世帯では住居費の負担が大きく、民間賃貸では家賃負担率が3割を超えるケースが多い とされています。
東京都区部の母子世帯では、年間収入約272万円に対して**家賃負担率が39〜43%**という調査結果もあります。
(出典:母子世帯の居住と就業の実態調査)
私も同じ看護師ママとして、「もう少し安心して暮らせる環境を整えたい」と思う方の気持ちがよく分かります。
この記事では、全国の自治体や厚労省データをもとに、ひとり親看護師が利用できる住宅支援制度・家賃補助をわかりやすく整理しました。
「どんな制度があるの?」「どうやって申し込むの?」という疑問を、実例付きで解説します。
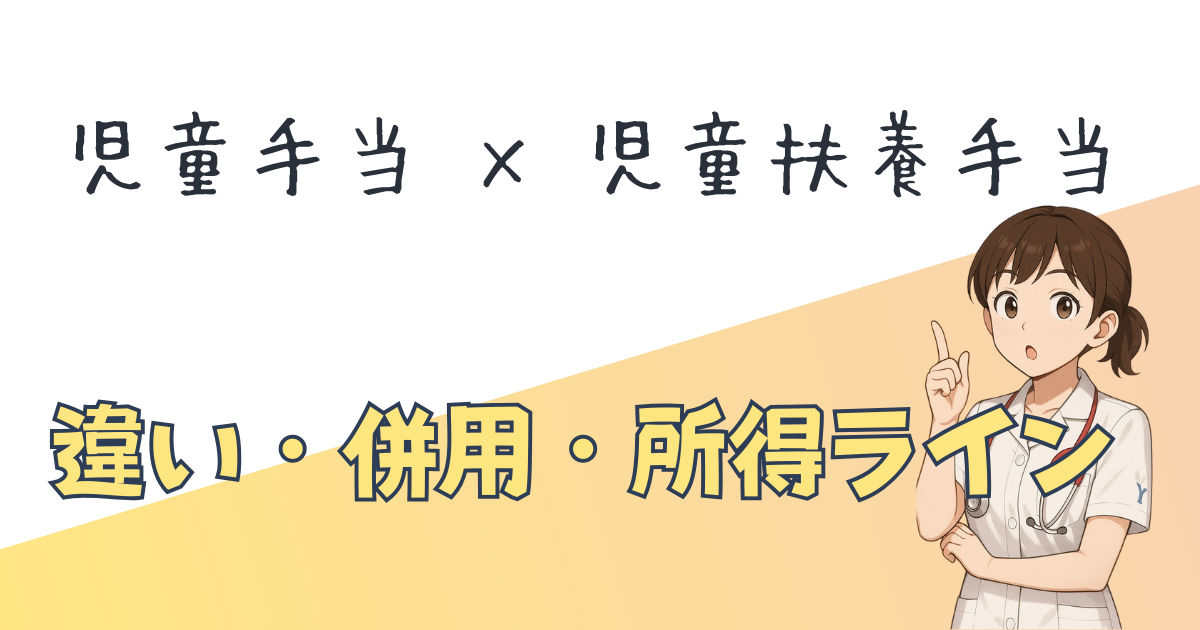
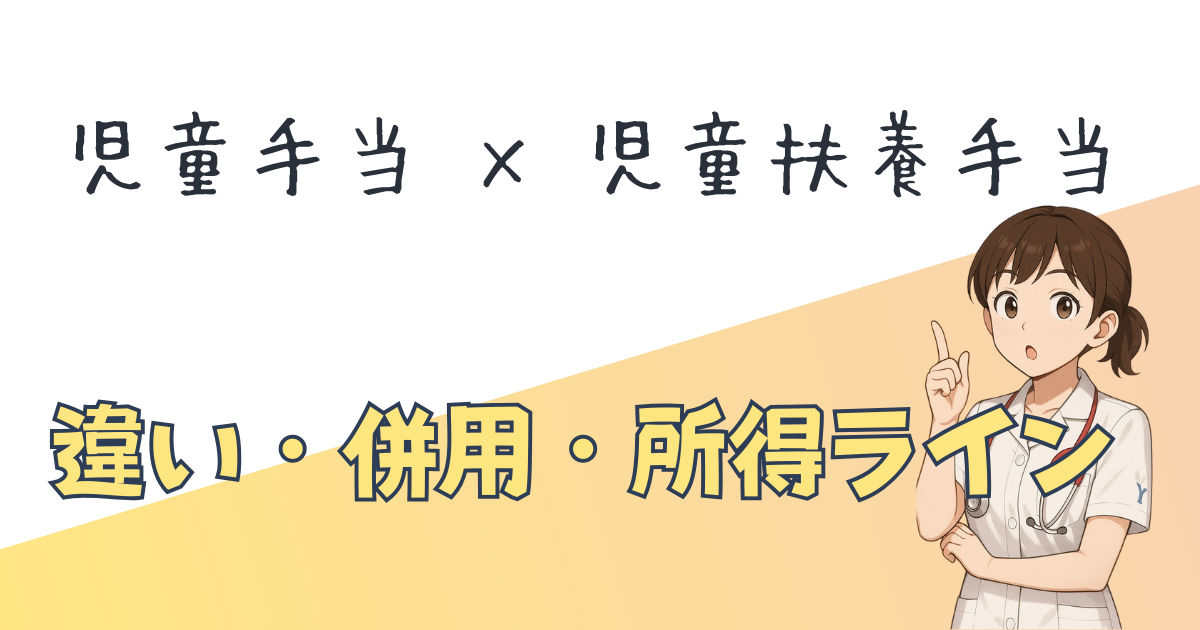
ひとり親看護師が“住まい”で悩みやすい理由
看護師として働く中で、「住まいの悩み」は意外と多いものです。
たとえば次のような状況、思い当たりませんか?
- 夜勤・シフト制のため、保育園や職場に近い物件を選ばざるを得ない
- 家賃の高い地域に住んでいるが、転居の余裕がない
- 収入はあるのに、児童扶養手当などが対象外で支援を受けにくい
🔍 厚労省の調査によると、母子家庭の平均家賃負担率は25〜30%前後。
家賃を1万円減らすだけで、年間12万円の節約効果になります。
(出典:厚生労働省 全国ひとり親世帯等調査)
そんな中でも「公的な住宅支援制度」を知っておくと、
家賃補助・無利子貸付・優先入居など、思わぬ選択肢が見えてきます。
ひとり親看護師が使える住宅支援制度・家賃補助3選


この記事で紹介する制度(3つの柱)
- 自治体の「ひとり親家庭住宅手当」(現金給付)
- 住宅支援資金貸付(無利子貸付・返還免除あり)
- 公営住宅のひとり親優先入居制度
🏠 ① 自治体の「ひとり親家庭住宅手当」
自治体が独自に行う家賃補助制度です。
対象者や金額は自治体ごとに異なりますが、ひとり親家庭の家計を大きく助ける支援です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 支給額 | 月5,000〜25,000円程度(自治体による) |
| 対象 | 児童扶養手当受給者、または同等所得 |
| 条件 | 賃貸住宅に居住していること |
| 期間 | 12〜36か月(更新制度あり) |
▶️ 具体例(住宅“手当”のみ)
江戸川区「ひとり親家庭住宅手当」
最大25,000円/月(所得制限あり)
※制度名は自治体により異なります(「母子家庭住宅手当」「家賃助成」など)。
💴 ② 住宅支援資金貸付(無利子貸付・返還免除あり)
ひとり親家庭の住居費や転居費用を対象に、無利子で貸付が受けられる制度です。
就労継続等の条件を満たせば返還免除となる自治体もあり、実質給付に近い制度です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 貸付額 | 家賃7万円程度まで(自治体により異なる) |
| 利子 | 無利子 |
| 返還免除 | 就労継続・支援プログラム修了で免除あり |
| 相談先 | 各都道府県の社会福祉協議会 |
▶️ 具体例(貸付制度)
札幌市「ひとり親家庭住宅支援資金貸付」
無利子・生活困窮時の家賃支援
大阪市「ひとり親家庭住宅支援資金貸付」
家賃・敷金礼金を対象に無利子貸付
🏢 ③ 公営住宅の「ひとり親優先入居制度」
県営・市営住宅やUR賃貸において、ひとり親世帯に「優先枠」を設けている自治体があります。
民間賃貸より家賃を抑えられる場合が多く、長期的に安定しやすい制度です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 家賃 | 所得連動で2〜5万円台が多い |
| 対象 | ひとり親世帯・児童扶養手当受給者 |
| メリット | 安定の長期入居・保証人不要制度あり |
| 注意点 | 抽選制のため早期応募が必要 |
▶️ 具体例(優先入居制度)
大阪市:市営住宅 ひとり親優先入居枠
さいたま市:市営住宅の母子・父子家庭優先入居制度
制度をスムーズに活用する3ステップ


まずは「自分の住んでいる自治体に、どんな住宅支援制度があるか」を調べましょう。
👉 検索キーワード例
- 「〇〇市 ひとり親 住宅手当」
- 「〇〇市 住宅支援 貸付」
- 「〇〇県 母子家庭 家賃補助」
「住宅」「貸付」「家賃」など、複数のワードを組み合わせて検索するのがおすすめ。
名称が「母子家庭住宅手当」「自立支援住宅費助成」など異なる場合もあります。
さらに、市区町村公式サイトの「子育て支援」「福祉」カテゴリをチェックすると、
「母子・父子・寡婦福祉資金貸付」など関連制度も一緒に確認できます。



見つからない場合は、「社会福祉協議会」または「子育て支援課」に直接電話を。
「ひとり親の住宅支援制度を知りたいのですが…」と伝えるだけでOKです。
制度の内容がわかったら、次は相談予約を取りましょう。
- 子育て支援課(ひとり親家庭全般の手当・給付)
- 福祉課(貸付・住まい支援の担当)
- 社会福祉協議会(住宅支援資金や就労支援の窓口)
看護師さんは夜勤やシフト勤務があるため、平日日中の来庁が難しいこともありますよね。
その場合は、次のように伝えるとスムーズです。
あなた 夜勤のため窓口に行く時間が限られるのですが、電話や郵送で申請できますか?



多くの自治体では、郵送や事前書類送付に対応しています。
また、相談日を電話で予約できるところもあるので、無理のないタイミングで動けます。
- 所得制限や支給金額の目安
- 申請から支給までの期間
- 必要書類の有効期限(所得証明書など)
申請時に必要な書類は、自治体ごとに多少異なりますが、
看護師ひとり親のケースでは次のようなものが一般的です。
- 戸籍謄本(ひとり親であることの確認用)
- 住民票(同居家族を確認)
- 所得証明書(課税・非課税の判定に使用)
- 賃貸借契約書(家賃額・住所確認)
- 児童扶養手当証書(または申請中である証明書)
- 看護師勤務証明書(勤務先で発行してもらう)
💡 コツ:
書類の原本を提出する場合は、コピーを手元に残しておきましょう。
追加提出を求められるケースが多いため、事前に複写を取っておくと安心です。
提出後は、数週間〜1か月ほどで結果通知が届くのが一般的。
支給決定後は、口座登録を経て毎月または数か月ごとに振り込まれます。



申請や書類の準備は、最初だけ少し大変ですが、慣れてしまえば次回更新もスムーズ。
「いまの暮らしを守るための仕組み」と思って、焦らず一つずつ進めていきましょう。
まとめ|制度を味方につけて、安心できる暮らしを
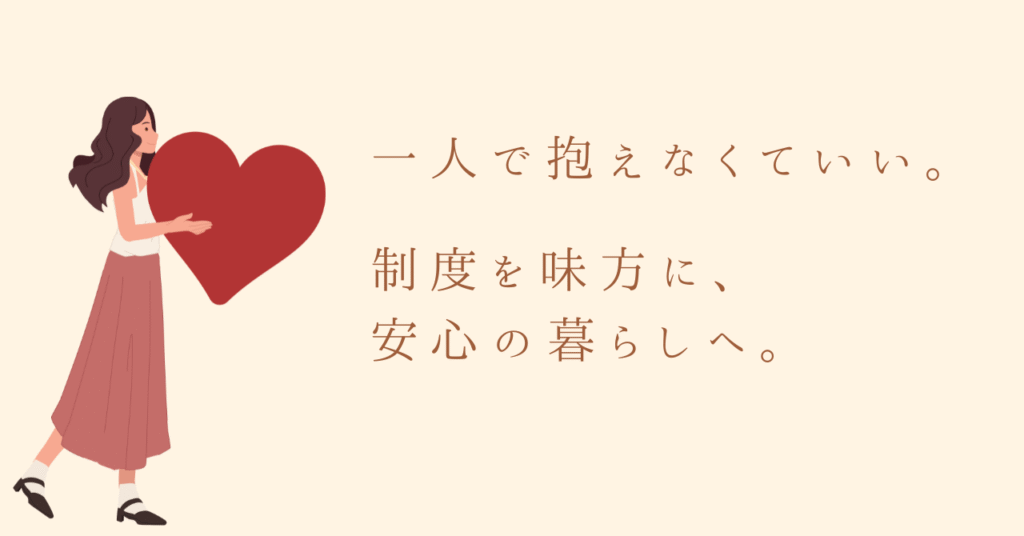
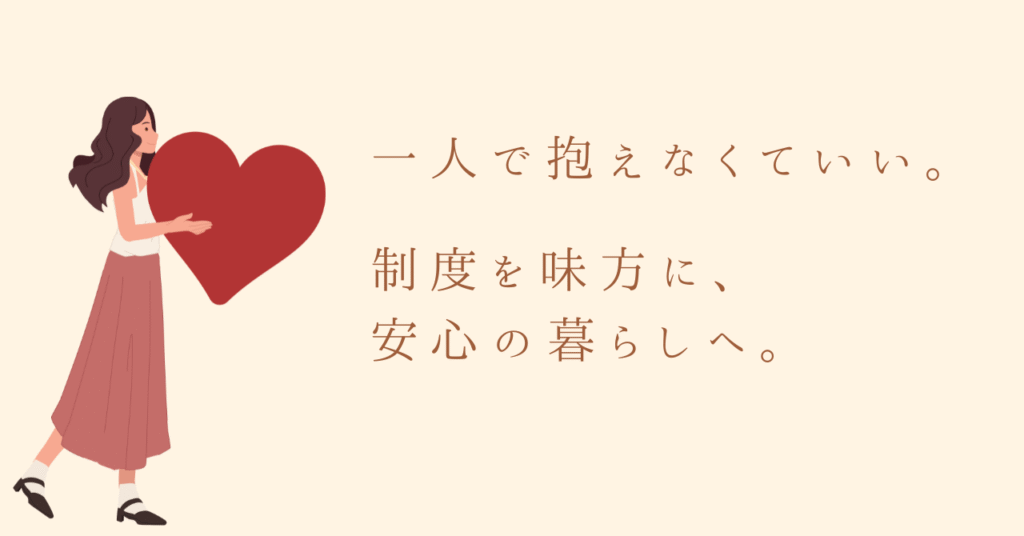
住宅支援・家賃補助は「自治体手当」「貸付制度」「公営住宅優先枠」の3つが柱。
所得制限があっても“部分支給”や“返還免除”のチャンスがあります。
夜勤・育児で忙しい看護師こそ、窓口相談のハードルを下げる工夫(電話・郵送)をして、
「できる範囲から動いてみる」ことが大切です。



無理をしなくても大丈夫。
少しずつ整えていけば、ちゃんと道は開けます。
今の暮らしを守るための制度は、あなたの味方です。
今日、ほんの少し調べてみる――それだけでも立派な第一歩ですよ。
まずはお住まいの自治体名+「ひとり親 住宅手当」で検索してみましょう。
相談予約を入れるだけでも、“今より安心して暮らせる第一歩”になります。
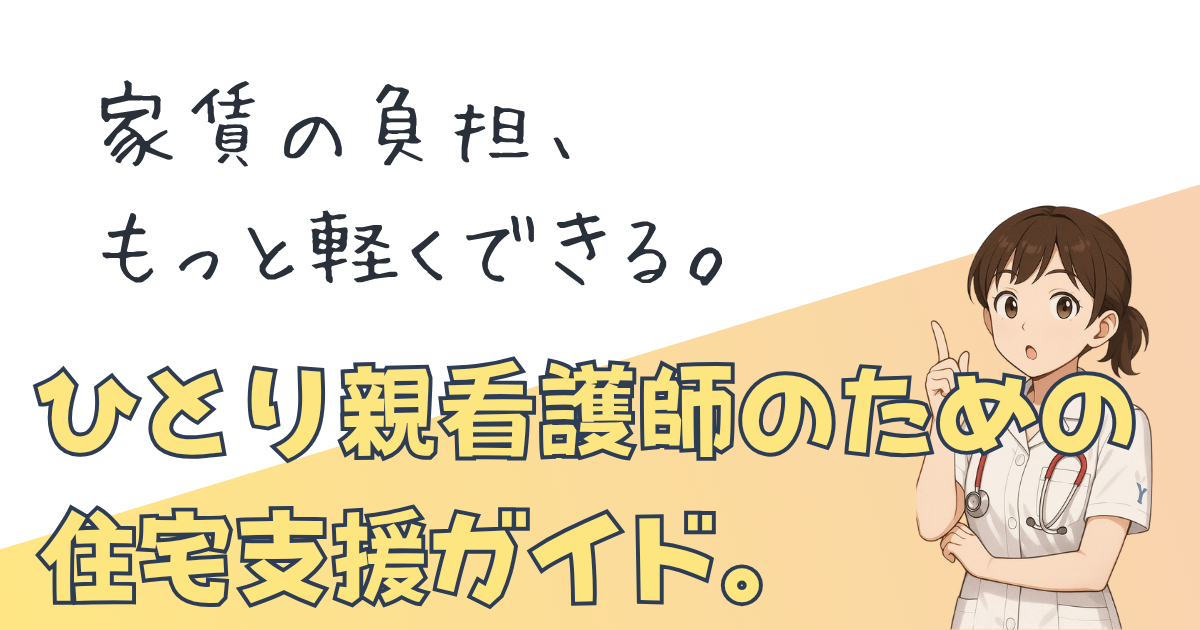
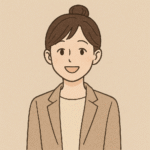
コメント