【PR】本記事にはプロモーションが含まれています。
 ゆいなん
ゆいなんこんにちは、看護師ゆいなんです。
私は病棟からクリニックへ転職し、看護師歴15年以上。4人の子どもを育てるシングルマザーです。夜勤の増減や子どもの体調不良、一時預かり費用……収入も支出も“読みにくい”のが現実ですよね。私も何度もヒヤッとしました。
この記事では、看護師×ひとり親のリアルに寄り添いながら、今日からできる家計管理のコツと、**ファイナンシャルプランナー(FP)**を味方につける具体策をお伝えします。
読み終える頃には、「これなら私にもできる」と感じてもらえるはずです。
- 看護師ひとり親が押さえるべき家計管理の土台
- 収入の“波”に強い設計(平均予算・予備口座・固定費)
- 失敗を減らす制度・手当のチェックポイント
- ファイナンシャルプランナーに相談するメリットと進め方
- 今日から動ける3つのアクション
時間がない方は、まず“無料相談”で土台作りから始めましょう。
なぜ看護師×ひとり親は家計管理に悩みやすいのか


夜勤と残業で収入が安定しにくい看護師ひとり親の家計事情
看護師として働くひとり親が家計管理に悩みやすい理由のひとつは、収入の波が大きいことです。夜勤や残業の回数によって手取りが変わり、月によっては3〜5万円の差が出ることもあります。夜勤が2回減るだけで手取りが4万円ほど減るケースもあり、固定費は変わらないまま。「今月はちょっと厳しいかも…」と感じる瞬間が増えてしまいます。



夜勤明けや休日出勤が多い月は収入が上がる一方で、体力的な負担も大きく、継続が難しいのが現実です。無理に働いても体調を崩してしまえば本末転倒。結果的に、収入も支出も安定しにくい構造になってしまうのです。
子どもの行事・体調不良で支出が増えるひとり親家庭の現実
さらに、支出の予測が立てにくいのも悩みの種です。子どもの行事や体調不良、一時預かりなどの予定外の支出が発生するたびに、家計のバランスが崩れがちになります。「働く時間を減らせば収入が減るし、働きすぎると子どもとの時間が減る」——どちらを取っても難しい選択を迫られます。



私も同じように、子どもの急な発熱で勤務を減らした結果、手取りが減って焦ったことが何度もありました。支出と収入、どちらも思い通りにコントロールできないのが、看護師ひとり親の家計の大きな特徴です。
仕事も家計も一人で背負う看護師ママのメンタル負担
ひとり親で家計を支えていると、「私が頑張らないと」というプレッシャーから、つい無理をしてしまうことがあります。仕事・育児・家計管理のすべてを一人で背負う状況では、冷静な判断が難しくなりがちです。



特に夜勤が減った月は、手取りが想定よりも少なくて青ざめたことを覚えています。家賃や保険料など“動かせない固定費”はそのままなのに、収入が減る。そんな状況が続くと、心まで疲弊してしまいます。
「収入の波」を前提に整える看護師ひとり親の家計設計術
そんなときに私が気づいたのは、「完璧に管理することよりも、“波を前提に整える”ほうが現実的」ということでした。
そこで、次の3つを徹底してみました。
- 平均手取りで予算を組む
- 収入が多い月は、余剰分を自動で“予備口座”に避難させる
- 固定費は年1回、必ず見直す



この3つを意識するだけで、月末のドキドキが驚くほど減りました。収入が増えた月も減った月も、焦ることなく「いつものリズム」でやりくりできるようになったのです。
無理に収入を増やすより“崩れない仕組み”を作るコツ
家計の安定は、収入を増やすことよりも「波があっても崩れない仕組み」をつくることが大切です。



看護師ひとり親という立場はたしかに大変ですが、医療職としての安定性や専門性という強みもあります。焦らず、一歩ずつ整えることで、日々の不安は確実に軽くなります。
看護師ひとり親がまず整えるべき家計管理の3ステップ


- 収入:基本給・夜勤手当・残業・児童手当・養育費
- 支出:固定費/変動費/特別費(学用品・行事・更新料など)
- 給料日に自動で「生活費」「予備」「教育・積立」口座へ振り分け
ポイント
- 夜勤手当は“なかったとしても回る設計”に
- 児童扶養手当や臨時収入は“教育・予備”へ直行
- 年間見込み手取り÷12=平均月収を基準に家計を組む
- 多かった月の超過分は予備口座へ自動振替
- 少なかった月は予備口座から補填して生活レベルを一定に
簡易目安
- 生活費:平均月収の80%
- 予備口座:5〜10%
- 教育・将来:10〜15%
- 特別費:5%
- 通信:スマホ・回線プランの最適化
→ 楽天市場で家計グッズ・SIM比較も便利 - 保険:働けないリスクを補いながらも、かけ過ぎを避ける
- 住居・光熱費:更新時期に見直す
看護師ひとり親が活用できる制度・手当まとめ【2025年版】


看護師×ひとり親の家計では、制度をどれだけ上手に使えるかが安定の鍵になります。ここでは、特に利用者が多い支援を整理して紹介します。
児童扶養手当:支給停止後も再申請できるケースとは?
18歳になった年度末までの子どもを育てるひとり親家庭に支給される手当です。
所得に応じて満額・一部支給・支給停止に分かれ、年に数回(通常は年3回)まとめて振り込まれます。夜勤や残業で一時的に年収が上がると減額されることがありますが、翌年の所得が下がれば再支給になるケースもあります。



支給停止になった場合でも、「減額停止届」を提出すれば翌年以降の再申請が可能です。
ひとり親控除:看護師ママが必ず押さえたい節税メリット
年末調整や確定申告で所得税・住民税を軽減できる控除制度です。
以前の「寡婦控除」よりも対象範囲が広く、婚姻歴がなくても扶養する子どもがいれば適用されます。



控除を受けるには勤務先へ「扶養控除等申告書」の提出が必要です。控除額は最大35万円(所得税)+10万円(住民税)と大きいため、忘れず申告を。
医療費助成:自治体で異なる支給範囲と所得制限の注意点
自治体ごとに名称は異なりますが、ひとり親家庭は子どもの医療費が実質無料または低負担になります。対象年齢は「中学生まで」や「高校卒業まで」など自治体によって異なるため、転居や学年の切り替え時は再確認が必要です。



所得制限がある自治体も多く、前年の所得で判断されます。夜勤手当が多かった年は注意しましょう。
保育料・学童の減免制度:シフト勤務看護師の強い味方
ひとり親家庭の場合、保育料・学童保育料の軽減や免除を受けられることがあります。保育園や学童の「特別利用枠」を活用できる自治体もあり、仕事が不規則な看護師には大きな支えになります。



申請時期は年度初めが多く、「前年度の所得証明」が必要です。収入が下がった年は途中申請も可能な場合があります。
高等職業訓練促進給付金:資格取得を支える収入補助制度
看護師資格の上位資格(認定看護師、助産師など)や別分野(介護福祉士、社会福祉士など)の取得を目指すひとり親が対象の給付金です。
養成期間中、月最大10万円程度(上限あり)+修了時一時金が支給されます。



自治体の「母子家庭等就業・自立支援センター」で相談・申請します。支給までに時間がかかるため、早めの相談が安心です。
自治体の家計相談・FP講習会:無料で専門家に相談する方法
近年は、自治体や社会福祉協議会が主催する無料の家計相談やファイナンシャルプランナー講習が増えています。「貯金ができない」「制度の優先順位がわからない」という相談もOK。中には保険・税・投資などをトータルで整理してくれるFPもいます。



市役所の「ひとり親支援担当」や地域の社会福祉協議会が窓口です。オンライン相談に対応している自治体もあります。
年度初めに見直す!制度を取りこぼさない3つのコツ
- 年度初め(4月)や学齢が上がる前後は、制度が更新されやすい時期。
- 前年対象外でも、翌年は対象になるケースが多い(夜勤・残業減などで所得が下がった場合)。
- 申請期限・所得判定日は自治体によって異なるため、必ず役所HPか窓口で確認を。
看護師ひとり親がFPに相談するメリットと活用法【家計改善の近道】


FPとは?看護師ひとり親の家計を総合的に支える専門家
看護師×ひとり親の家計は、収入の波と制度の複雑さが重なりやすく、どこから見直せばいいのか迷う人が多いです。
そんなときに頼れるのがファイナンシャルプランナー(FP)。FPは、家計・保険・税金・制度・資産形成を“横断的”に整理してくれるお金の専門家です。
FPができること:看護師×ひとり親の家計を整える5つの視点
FPは「節約のアドバイス」だけでなく、あなたの働き方や家族構成に合わせて、家計全体の仕組みを再設計してくれます。
たとえば、
- 夜勤や残業が減ったときの平均手取りで生活を安定させる予算設計
- 子どもの成長に合わせた教育費の積立プラン(小→中→高→大学)
- 加入中の保険の過不足チェック(学資・医療・生命の重複や無駄)
- NISAやiDeCoなどの投資を生活費と両立させる仕組みづくり
- 児童扶養手当・税控除との併用整理(手当を減らさずに資産形成)



こうした部分を、専門的な知識と数値で整理してくれるので、「何から始めればいいのか」「どれを優先すべきか」が明確になります。
実際の相談はどう進むの?
初回の面談では、現在の収入・支出・保険内容をヒアリングし、あなたの希望(たとえば「夜勤が減っても赤字にならないようにしたい」「教育費を無理なく積み立てたい」など)をもとに、現実的で続けられる家計プランを一緒に作ります。
面談は対面だけでなくオンラインも多く、30分〜1時間ほどで完了。
保険の見直しを含めても、強引な勧誘がない相談先を選べば安心です。



特に、育児や夜勤で時間が取りづらいひとり親にとって、スマホで完結できる無料相談は非常に心強い味方になります。
FP相談を活用するメリット:数字で“腹落ち”する家計設計
FPに相談する最大の利点は、「数字で腹落ちできる」こと。
自分ひとりで家計を考えると「これで大丈夫かな?」と不安が残りますが、FPと一緒に「いつまでに・何を・いくらで」という形に落とし込むと、判断が格段に早くなります。
また、税金や控除、制度との兼ね合いを踏まえた提案をしてくれるため、“もらえるお金を減らさず、増やす”家計設計が可能になります。
FP相談の流れ:初回面談から行動プランまでのステップ
- 目的を1行で伝える(例:「夜勤が減っても赤字にならない家計にしたい」)
- 材料を準備(通帳・家計アプリ出力・保険証券・年金定期便)
- 希望を伝える(保険だけでなく家計全体を見てほしい)
- 行動表をもらい、実行タイミングを整理
無料相談リンク
【体験談】FP相談で家計がラクに!看護師ひとり親が月3万円浮いた実例


FP相談前:家計の死守ラインが曖昧で不安だった頃



夜勤が減り、手取りがダウンした時期がありました。
家計の「死守ライン」が曖昧で、引き落とし日が近づくたびに不安でいっぱい。
それでも、「自分の家計を他人に見せるなんて恥ずかしい」と思っていた私は、FP相談に踏み切るまでに時間がかかりました。
正直、相談しても劇的に変わるとは思っていませんでした。
でも実際に話してみると、FPさんは「無理なくできる改善」だけを一緒に整理してくれて、気づけば心のハードルがすっと下がったんです。
FP相談後:平均月収設計と固定費見直しで月3万円浮いた話



最初に取り組んだのは、平均月収を基準に家計を見直し、超過分を予備口座へ自動移動する仕組み。
次に、通信費・保険・サブスクの棚卸しをして、不要なプランや重複契約を削減しました。
結果、スマホ代と保険の見直しだけで月3万円以上浮いたんです。
そこからは、学齢に合わせて教育費の積立を段階的に増やす流れを作り、家計のバランスが見えるようになりました。
何より大きかったのは、数字で把握できるようになったことで、「この範囲なら大丈夫」という安心感が得られたこと。
行事や急な病気にも慌てず対応できるようになり、家計に“余白”ができました。
お金のことを“我慢や不安”ではなく、“整えること”として考えられるようになったのは、この相談がきっかけです。
今日からできる!看護師ひとり親の家計改善3アクション


- 固定費の棚卸し(今週末1時間)
通信・保険・サブスクを見直し。月1万円削減=年12万円の余力。
楽天市場で比較して必要なものを絞る
https://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=45BS6X+C7ZCTU+2HOM+65EOH - 予備口座の自動振替
平均月収を超えた分を自動で予備口座へ。少ない月の補填に使う。 - FP相談を予約(30分でもOK)
オンライン相談で子どもがいても安心。
- ベビープラネット(無料)
https://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=45I51I+ABII9E+503M+5ZEMP
- Find it(無料あり)
https://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=45I51I+AEHOAA+5MAS+5Z6WX
よくある質問|看護師ひとり親の家計管理・FP相談Q&A


まとめ:収入の波を“前提”にすれば家計は強くなる
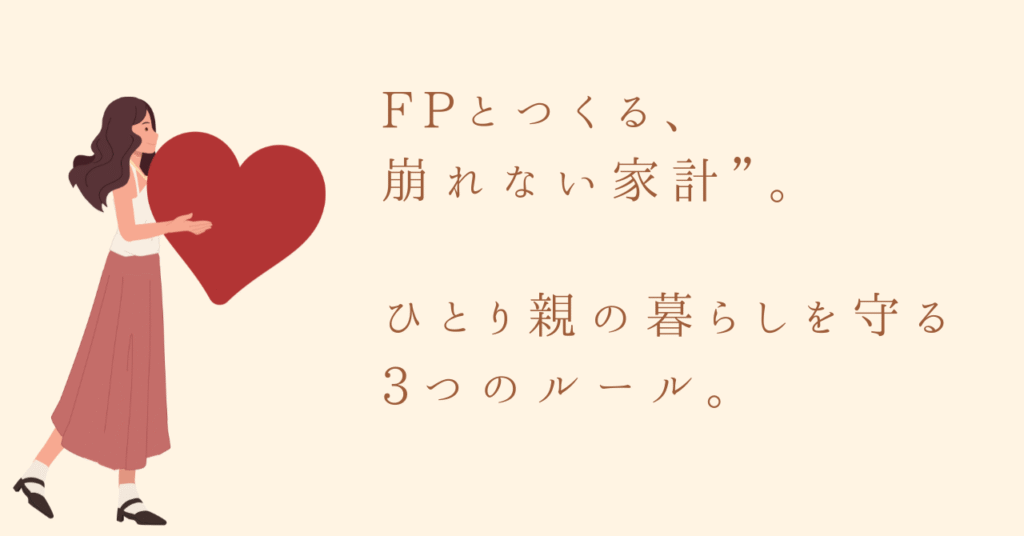
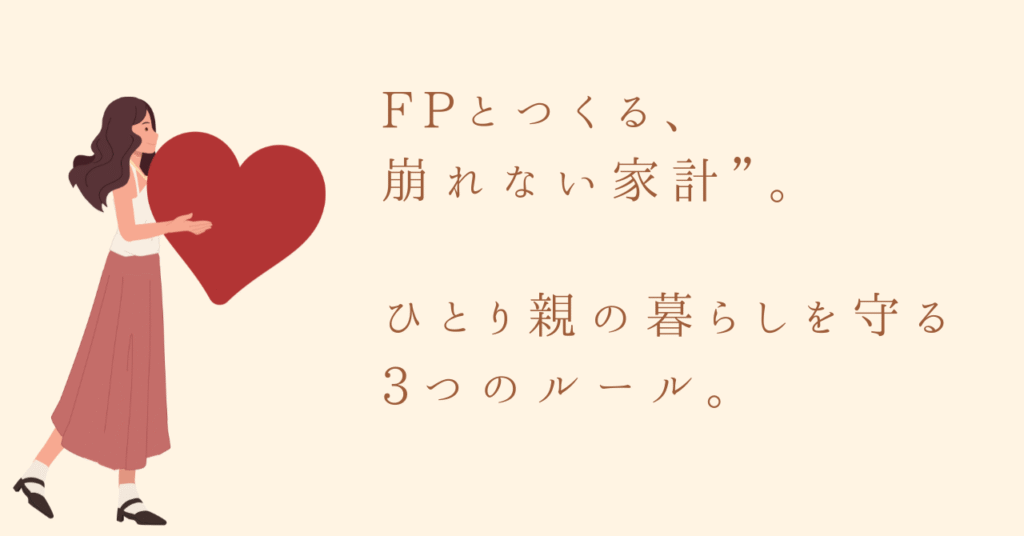
- 看護師ひとり親の家計管理は、収入の波を前提に平均で設計
- 固定費棚卸し・予備口座・制度確認で守りを固める
- FPと一緒に保険・教育費・資産形成を現実的に続ける設計へ
今日の小さな一歩が、数か月後の大きな安心につながります。
あなたの暮らしが、少しずつ穏やかで確かなものになりますように。
※本記事は、私自身の体験と一般的な家計管理の考え方をもとにまとめています。制度・手当は自治体や年度で異なるため、最新情報は公式サイトでご確認ください。必要に応じてFPなど専門家へご相談ください。
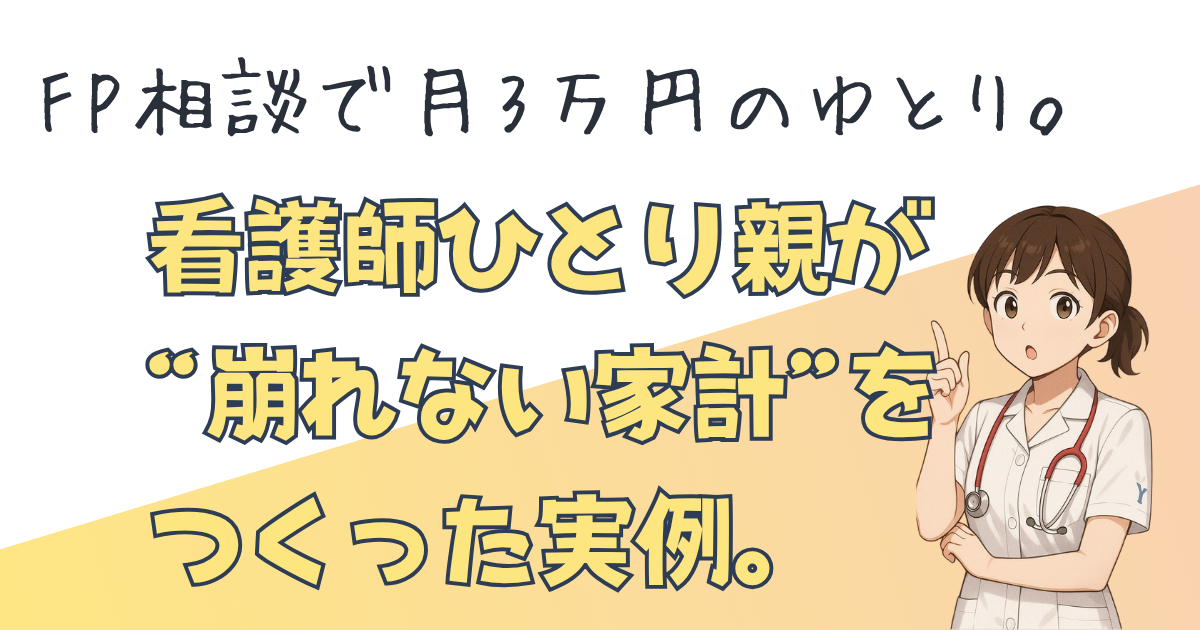
コメント